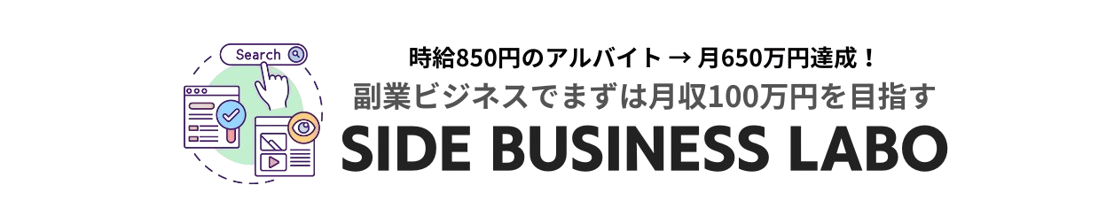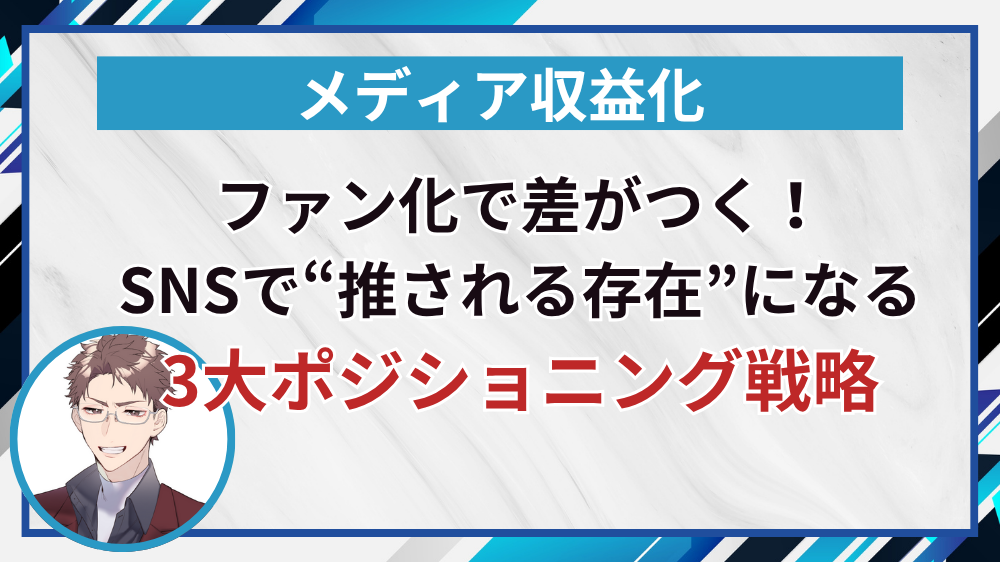SNSの時代、フォロワー数が多い=成功という時代は終わりつつあります。今、注目されているのは「ファン化」、つまり“この人をずっと見ていたい”“この人の考え方が好き”と思ってもらえる存在になることです。瞬間的なバズではなく、じわじわと信頼を積み重ねていく「ファン化」は、SNSで長く活躍したい人にとっての武器になります。
今回は、私が実際にSNS運用で効果を感じている「ファン化のコツ」について、3つのポジショニング戦略に沿って詳しく解説していきます。まずはファン化とは何か、その本質と重要性から見ていきましょう。
ファン化とは?SNS時代における個人の武器になる理由
ファン化は「バズ」とは違う長期的な信頼構築戦略
SNS上では、1回のバズで一気に注目を集めることも可能ですが、バズは一時的な現象に過ぎません。フォロワーが一時的に増えても、その後の発信が刺さらなければ離脱してしまうのが現実です。
一方、ファン化は「この人の考えが好き」「この人のポストは毎回見たい」と感じてもらえるような、継続的な関係性の構築を目指す戦略です。つまり、“数”ではなく“信頼”を積み上げることで、長期的に支持される土台を作るのがファン化なのです。
アルゴリズム時代のSNSでファンを作る意味
X(旧Twitter)やYouTubeなど、現在の主要SNSはAIによるアルゴリズムで投稿が拡散される仕組みになっています。バズを狙った投稿が多く見られる中で、アルゴリズムは「この人の発信は誰に向いているのか」「フォロワーとどれだけ関連性があるか」といった文脈的な情報をもとに拡散範囲を決定しています。
つまり、単に拡散されることよりも「誰に届くか」「どう届くか」が重要なのです。この点で、ファン化されたフォロワーは関連性が高く、アルゴリズム上も強く評価されやすくなります。結果として、安定的にポストが広まりやすくなります。
フォロワー数より「記憶に残る存在」が大事な理由
何万人とフォロワーがいても、「あの人誰だっけ?」と思われてしまっては意味がありません。逆に、フォロワーが1000人でも「この人の投稿はいつも気になる」「名前は忘れない」と思ってもらえるアカウントには大きな価値があります。
ファン化とは、まさに「記憶に残る存在」になること。フォロワーと深い関係性を築き、その記憶の中に居続けることで、支持される存在になっていきます。
最強のファン化テクニック=ポジションを取ること
“〇〇と言えば自分”という立ち位置の作り方
ファン化の第一歩として、まずやるべきことは「ポジションを取ること」です。これは、「〇〇といえばこの人だよね」と思われるような立ち位置を築くことを指します。たとえば「Xの伸ばし方といえばあの人」「AI活用といえばこの人」といったように、自分の専門性や考え方を明確にすることで、記憶に残る存在になっていきます。
実績ゼロでもできる!初心者こそ意識すべきポジショニング
「ポジションを取る」というと、何かすごい実績が必要だと思われがちですが、実はそんなことはありません。重要なのは、“考え方”や“発信の切り口”を明確にして、一貫性を持って伝えることです。実績がなくても、「こういうスタンスで発信しています」という姿勢があるだけで、フォロワーからの印象はガラリと変わります。
例えば、「フォロワーの質が大事」という立場をはっきり打ち出すだけでも、そこに共感する人たちが自然と集まり始めます。初心者だからこそ、最初にこの軸を持つことが、他との差別化になります。
中途半端は埋もれるだけ。振り切ることがファンを呼ぶ
「量も質も大事」「バランスが大事」という発信は一見正しく見えますが、SNS上では中途半端に見えてしまい、印象に残りにくいのが現実です。どちらかに振り切ったほうが、発信に芯が通り、共感する人からの信頼を得やすくなります。
もちろん、すべての人に好かれる必要はありません。むしろ「この人の考えには共感する」「賛否両論あるけど筋が通ってる」と思われるほうが、強いファンを作る近道です。
ポジショニング実践①:AはBパターンで立場を明確にする
よくある意見の“対立構造”に切り込む
ここで実践的なテクニックをご紹介します。まずは「AはBパターン」。たとえば「フォロワーは多い方がいい」vs「フォロワーは質が大事」というように、よくある対立する意見に対して、どちらかに立場をはっきりさせて発信していく方法です。
どちらかに振り切ることで「共感or記憶」に残る
どちらも一理ある話ではあるのですが、「私は〇〇の立場で発信します」と明確に示すことで、ポストに一貫性が生まれ、強烈な印象を残すことができます。これはファン化において非常に大事なポイントです。賛否両論が出るかもしれませんが、それこそが“議論を生むアカウント”になり、より濃いフォロワーとつながれるきっかけになります。
情報発信型アカウントとの相性が抜群な理由
特に情報発信を中心にしているアカウントは、ポジショニングが曖昧だと他のアカウントとの差別化が難しくなります。「このテーマならこの人」と思ってもらえるような立場の取り方ができると、信頼性も高まり、シェアや引用の対象にもなりやすくなります。
ポジショニング実践②:「これが好き」パターンで熱量を伝える
一点突破の「好き」がキャラクターを作る
ポジショニングにおいて、誰でもすぐに取り入れやすいのが「これが好き」パターンです。これは、自分の“好き”を1つに絞り、それを全面的に打ち出していく方法です。
例えば「動物が好き」ではなく「猫が好き」、さらに「猫の肉球がたまらない!」といったように、具体的に、そして情熱的に伝えることが重要です。この「好き」は、あなたのキャラクターそのものになります。なぜなら、人は“熱量”のある人に共感しやすく、「この人、本当にこれが好きなんだな」と伝わるだけで好感度が上がり、覚えてもらえる確率が高くなるからです。
SNSでは無数の情報が飛び交っているため、曖昧な好みでは記憶に残りません。「好き」を一点突破で明確にすればするほど、発信の一貫性が高まり、結果として「〇〇が好きな人=あなた」という図式が自然と定着していきます。
雑になりがちな日常系アカウントにも活用できる理由
「これが好き」パターンは、情報発信系ではない“日常系アカウント”との相性も抜群です。日常系の発信は、どうしてもテーマがぼやけがちになり、差別化が難しいという課題があります。
しかし、この「好き」を軸にすれば、日々の生活の中にも統一感が生まれます。例えば「コーヒーが好き」なら、「今日の朝コーヒー」「お気に入りのカフェ」「コーヒー豆のレビュー」など、日常の投稿に統一感と“らしさ”が出てきます。
雑多になりがちな投稿でも、「この人といえばこれ」と思ってもらえるようになることで、ファン化が進みやすくなります。
尖りすぎないマイルドなファン化導線
また、「これが好き」パターンは、前編で紹介した「AはB」パターンよりもマイルドな印象を与えることができるという特徴もあります。対立構造を利用するような尖った発信が苦手な方でも、柔らかく自然な形でポジションを確立することができるのです。
日々の投稿を通じて「この人の“好き”に私も共感できる」と思ってもらえれば、それは立派なファンの始まりです。「好き」というポジションは、最初は小さくても、継続的に発信を重ねることで大きな信頼と共感に育っていきます。
ポジショニング実践③:「目標パターン」で共に旅するストーリーを
目標は「ふわっと」より「具体的」に
3つ目のポジショニング戦略は「目標パターン」です。これは、自分の目標を発信に織り込み、それをフォロワーと共有していくことでファン化を進める手法です。
ここでのポイントは「目標は具体的に」です。例えば「いつか本を出したい」ではなく「半年以内にX運用のノウハウをまとめた電子書籍を出版する」というように、期間や手段、ゴールを明確にすることで、フォロワーがあなたの成長や努力を“応援しやすく”なります。
目標がはっきりしていれば、投稿内容にも自然とストーリー性が出てきます。何をしているのか、何を目指しているのかがわかるので、「次はどうなるんだろう?」という関心も高まりやすくなります。
進捗報告が共感を生む最大のポイント
この「目標パターン」の醍醐味は、進捗をリアルタイムで共有することにあります。たとえば「今月は3件の取材に成功しました」「今日は1ページ書けました」「失敗してしまったけど、ここから立て直します」など、日々のちょっとした変化や気づきをシェアすることで、フォロワーとの心理的距離がグッと近づきます。
SNSでは、完璧な結果だけを見せるよりも、試行錯誤や葛藤、成長過程を見せた方が共感されやすい傾向があります。特に個人アカウントでのファン化を目指すなら、感情の共有が非常に大きな武器になります。
フォロワーが一緒に「ゴールを見たくなる」仕掛け
この手法が優れているのは、フォロワーを「傍観者」ではなく「参加者」に変えられる点です。あなたの挑戦を日々見ているフォロワーは、次第に「この人のゴールを一緒に見届けたい」と思うようになります。
たとえば「半年でギターを弾けるようになる」という目標であれば、日々の練習風景、失敗、上達の記録をポストし続け、最後に1曲披露できた瞬間を動画で投稿すれば、大きな感動と一体感が生まれるでしょう。そうやって物語性を持たせることで、あなた自身がSNSの中で“応援したくなるキャラクター”として認識されるようになります。
アカウントの“プロット”を作ってブレない世界観を言語化しよう
プロットとは?発信活動の軸を整える戦略図
ここまで紹介してきた3つのパターン(AはB・これが好き・目標)を効果的に活用するには、それぞれのポジショニングを組み合わせて自分だけの“プロット”を作るのがおすすめです。
プロットとは、小説などで使われる「物語の筋」のことを指しますが、SNS運用でも「どんな人が」「どんな信念で」「どこに向かっているのか」といった発信の設計図のようなものになります。
あなたのSNSの存在意義や方向性を明文化することで、発信がぶれなくなり、世界観に一貫性が生まれます。
自分の価値観・発信理由・目標を1つにまとめる
プロットを作るには、「なぜ自分がこのテーマを発信しているのか」「どんな人に届いてほしいのか」「どんな未来を描いているのか」という3点を意識して文章化してみましょう。
例えば以下のような形です:
「誰よりも地味に努力するタイプの私が、Xの最新アルゴリズムに挑戦しながら、クリエイターが自分らしく生きられる道を切り拓く。そしてその過程をリアルに共有することで、同じように頑張る人の背中を押したい。」
このようなプロットがあるだけで、日々の発信の方向性に迷いがなくなり、自分でも自信を持ってSNSを運用していけるようになります。
日々の投稿にプロットを落とし込んでファンに伝える方法
プロットができたら、それをプロフィールや投稿に自然な形で反映していきます。プロフィールには「何が好きか」「どんなことをしているのか」「何を目指しているのか」を簡潔に記載し、投稿では日常の中でその価値観や目標が垣間見えるような表現を心がけます。
これにより、SNSの中で「この人の世界観が好き」「考え方に共感できる」と感じてもらえるようになります。結果として、ただの“フォロワー”が“ファン”へと変わっていくのです。
まとめ:3つのパターンを使って「推されるアカウント」になろう
SNSでファン化を目指すには、ただの情報提供や拡散力だけでは限界があります。特に近年はアルゴリズムが「エンゲージメント」や「関連性」を重視する中で、表面的な数字よりも“深い共感”や“継続的なつながり”が評価される傾向が強まっています。
その中で、今回ご紹介してきた3つのポジショニングパターン——「AはBパターン」「これが好きパターン」「目標パターン」は、どれもファンを生み出すための実践的かつ再現性の高い戦略です。
では、最後にこれらの戦略を統合し、「推されるアカウント」として長く愛される存在になるためのポイントを整理していきましょう。
「方向性の一貫性」が世界観と記憶に残る存在を作る
最も大切なのは、“どのパターンを使うか”以上に“方向性を一貫させること”です。SNSでは日々膨大なコンテンツが流れていくため、何を投稿したかではなく、「誰が投稿したか」が記憶に残るかどうかが勝負になります。
つまり、「この人といえば〇〇」という印象を強く残すためには、自分がどの立場で、どんな世界観を持っているかを常にブレずに発信し続ける必要があります。
・AはBパターンでは、立場をはっきりさせて議論の中心になる
・これが好きパターンでは、熱量と情熱を持って好きなものを語り続ける
・目標パターンでは、ストーリーで人の感情を巻き込み、共に歩んでいく
どのパターンを使っても、発信に“芯”があることで、その人らしさ=世界観が育ちます。一貫した方向性は、アルゴリズムにも伝わりやすく、関連性のあるフォロワーに届く確率も格段に上がるのです。
あなたのプロットを作って、言語化することから始めよう
ここで最も重要になってくるのが“プロットの言語化”です。プロットとは「自分が何者で、なぜ発信し、どこへ向かうのか」を整理した戦略図のようなもの。
これをしっかりと言語化しておくことで、迷ったときの指針になり、発信の方向性にブレがなくなります。
たとえば、あなたのプロットが以下のように整理できるとします:
「趣味のカメラで見つけた“心が動く瞬間”を記録し、同じように感動を覚える人と繋がりたい。最終的には自分の写真展を開催することが目標です。」
このプロットがあるだけで、発信テーマ(カメラ)・共感軸(心の動き)・目標(写真展)という3つの軸がはっきりし、投稿内容にも深みと一貫性が出てきます。フォロワーはこの背景を知ることで、あなたに対して親しみを感じやすくなり、応援したくなる心理が自然と働きます。
プロットは一度作って終わりではなく、定期的に見直しながらブラッシュアップしていくものです。活動が進むごとに、価値観や目標が変わるのは当然のこと。それに合わせてプロットも進化させましょう。
ファン化は「広く浅く」より「狭く深く」
SNSでは多くの人に好かれたいという気持ちから、発信のスタンスを曖昧にしてしまう人も少なくありません。しかし、誰からも嫌われない発信は、誰にも強く支持されないという現実があります。
本当の意味で“推される存在”になるには、あえて「誰かに嫌われてもいい」と割り切って、自分の軸を強く打ち出すことが大切です。大衆受けを狙うのではなく、“少数でも深く共感してくれるファン”を増やしていく意識にシフトすること。
フォロワー数が少なくても、毎回の投稿にリアクションしてくれたり、あなたの考えに深く共感してくれる人がいれば、それだけでアカウントは成長していきます。なぜなら、その濃いファンこそが拡散の起点となり、新しいフォロワーを連れてきてくれるからです。
3つのポジショニング戦略を組み合わせて独自の“推され道”を築こう
ご紹介した「AはBパターン」「これが好きパターン」「目標パターン」は、それぞれ単独でも強力な武器ですが、状況やテーマに応じて組み合わせて使うことで、より厚みのあるアカウントに育てることができます。
たとえば、ある投稿では「AはB」で立場を示し、別の投稿では「これが好き」で人間味を見せ、さらに「目標パターン」で未来のビジョンを共有する。こうした複数の角度からの発信は、フォロワーとの多面的な接点を作り、より深いファン化につながります。
あなたのSNS活動が、ただの情報発信ではなく、ひとつの“物語”として共感され、応援されるようになるには、自分自身の考えや価値観を言葉にし、それを発信に落とし込むことが不可欠です。
最後に:あなたの「らしさ」は最大の武器になる
SNSには正解がないからこそ、“あなたにしかない視点”や“あなたにしかできない発信”が最大の武器になります。
他の誰かの成功パターンをなぞるのではなく、自分の内側にある想いや経験から発信を始め、徐々に自分らしい世界観を作り上げていく。そのプロセスこそが、ファン化を進め、最終的に「推される存在」への近道になるのです。
この後編では、プロットの活用法と、3つの戦略の総まとめを通じて、あなたがSNS上で唯一無二の存在になるための考え方をお伝えしました。あとは、実践あるのみです。
あなたが発信する“世界”を、誰かが楽しみにしている。そのことを信じて、まずは小さな一歩からスタートしてみてください。ファンは、あなたの内側にある“本音”と“こだわり”に惹かれて集まってくるものです。
自分だけの「ポジショニング戦略」を武器に、あなただけの物語をSNSで育てていきましょう。